【転職】職務経歴書は折らないが、必要なときの折り方は?
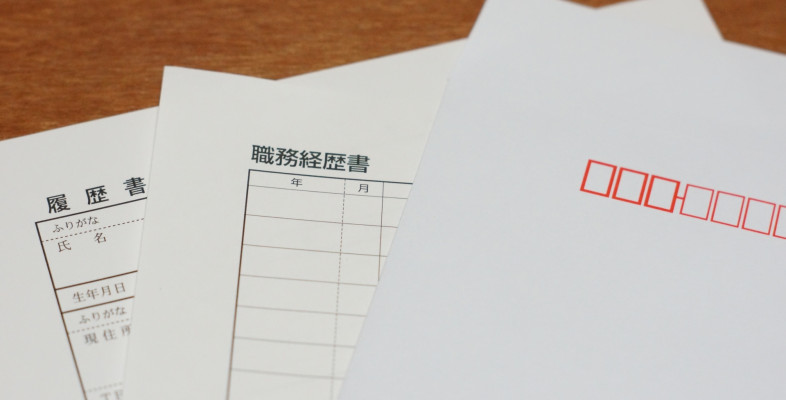
職務経歴書を郵送するさいは、折らずに封筒に入れることが一般的ですが、職務経歴書を折って入れても良いのか、また折り方がわからなくて悩む人は多いようです。
はたして職務経歴書は折って封筒に入れても問題ないでしょうか?
職務経歴書を折って封筒に入れる場合の適切な折り方はあるでしょうか?
職務経歴書で見栄えの良い折り方をするにはどうしたら良いでしょうか?
折り方以外にも、職務経歴書を郵送する場合に気をつけたいことを知りたいものです。
本ブログは、職務経歴書は折らないほうが良いけれど、必要なときの折り方などについて解説します。
転職活動では、自己分析や企業研究した結果を基に履歴書や職務経歴書を作成し、一貫性をもたせて面接に繋げることを強く意識して臨んでください。
本サイト「キャリア育みファーム」を読んでいただければ、転職活動の選考・面接対策に自信が持てるようになります。さらに、絶対の自信を持って臨みたい方には、「転職面接必勝法」を用意しております。
職務経歴書・履歴書のサイズの選び方
職務経歴書の郵送で必要なときの折り方について知るまえに、職務経歴書・履歴書のサイズの選び方を説明します。
職務経歴書などのサイズは、折り方にも影響するからです。
転職活動で使用する職務経歴書や履歴書のフォーマットやサイズは指定する企業もありますが、ほとんどの場合用紙の指定はありません。
- 職務経歴書
職務経歴書は、企業から特に指定がない限りA4(210mm×297mm)サイズが一般的です。
企業が知りたい本人の職務経歴や、スキル、自己PR、志望動機などを十分なスペースを使ってアピールするためにはB5(182mm×257mm)サイズではむずかしいからです。
またビジネスで使用される書類の多くはA4サイズであり、企業が管理しやすいサイズと言えます。
職務経歴書をパソコンで作成する場合は、A4の用紙を使用してください。
市販されている職務経歴書はA4(A3サイズの二つ折り)とB5(B4サイズの二つ折り)が一般的ですが、企業からの指定が特にない場合は、A4を選択すると良いでしょう。
- 履歴書
履歴書をパソコンで作成する場合は、A4の用紙を使用してかまいません。この場合、用紙を2枚に分けざるを得ないかもしれませんが、選考に不利になることはありません。
市販の履歴書はA4(A3サイズの二つ折り)とB5(B4サイズの二つ折り)があります。履歴書は企業から指定がなければどちらでもかまいません。
職務経歴書はA4、履歴書はB5となることがあり、サイズを合わせる必要があるのか迷うところですが、特に合わせる必要はありません。
職務経歴書は折って封筒に入れても問題ないか
職務経歴書は折って封筒に入れても問題ないのか探ってみます。
- 職務経歴書は折らない、または二つ折りの折り方で封筒に入れることが望ましいです。
職務経歴書はA4サイズ、またはA3サイズの二つ折りだと採用担当者もスッキリと見やすくなります。
職務経歴書や履歴書のような応募書類は、A4サイズのクリアファイルに挟んで封筒に入れて郵送することが基本です。(A3サイズまたは、B4サイズは二つ折りの折り方とします)
「角形2号」の封筒を使用すると、職務経歴書や履歴書などを挟んだクリアファイルが問題なく入りますので、「角形2号」を使用しましょう。
- 定型封筒に、三つ折りにした職務経歴書を入れて郵送することはマナー違反ではないが、避けた方が無難です。
市販の職務経歴書や履歴書を購入すると、三つ折りの折り方を想定した用紙の入る定型封筒が、一緒に入っているものもあります。
転職活動を始めたばかりの人は、これに入れて提出するものだと当たり前のように考えてしまいますが、職務経歴書などに折り目が増えて見栄えが良くありません。
また採用担当者が、応募書類を面接官用にコピーするさいや、ファイリングするさいに書類を伸ばさなくてはなりません。
職務経歴書や履歴書を三つ折りにしてもマナー違反ではありませんが、避けた方が無難です。
ですが、パート・アルバイト募集に応募のさい、または派遣会社や人材紹介会社に提出する場合は、定型封筒に三つ折りの応募書類はそれほど気にされないでしょう。
一方で、職務経歴書や履歴書では、一般的には四つ折りをしません。四つ折りでないと入らない封筒しか手許にない場合は、適切な封筒を購入してください。
職務経歴書を折って封筒に入れる場合の適切な折り方
上記のように職務経歴書は折らない、または二つ折りにして封筒に入れる折り方が望ましいですが、ここでは三つ折りにして入れる場合の適切な折り方を説明します。
ビジネス文書を三つ折りにする場合は、封筒から文字が透けて見えないように白い面を外側に文章面を内側に折る、巻き三つ折りが一般的です。
(巻き三つ折りとは、紙面を三分割し、一つの面を内側に折り、反対側の面を被せるように折る折り方です)
ですが、職務経歴書や履歴書を三つ折りにする場合は、名前や写真が開封したときすぐに確認できる文章面を上にする外三つ折りにする場合が多いようです。
(外三つ折りとは、紙面を三分割し、山折りと谷折りでジグザグに折る折り方です。Z字型に折るため、「Z折り」とも呼ばれる折り方です)
職務経歴書がA4で複数枚あるときは、まずクリップで紙の左上を留め、複数枚を同時に折ります。
職務経歴書の見栄えの良い折り方
職務経歴書・履歴書は、ただ三つに折れば良いというものではありません。折り目がきたなかったり、しわになったりすると見栄えが良くありません。
折り方ひとつで採用担当者は、応募者のアバウトな性格や、自社への志望度合いを推し量ってしまうものです。
そのため、できるだけ丁寧に折ることが望まれます。定規を使って折り目を美しく整えましょう。
具体的な折り方は次の通りです。
①職務経歴書(履歴書)がA3またはB4ならば、裏返して端をそろえてA4またはB5サイズになるように半分に折る
②氏名(写真)を表面にして上から1/3を残し、下2/3を後ろに折る。折り目はA4サイズなら1/3は99 mm、B5サイズなら86 mmが目安。折り幅は定規で測る
③下2/3のうち、1/3を奥側に折り返す
これで三つ折りができます。横から見ると丁度アルファベットの「Z」のような形になります。
折り方以外にも職務経歴書を郵送する場合に気をつけたいこと
職務経歴書の折り方以外にも、職務経歴書を郵送する場合に気をつけたいことがあります。
- 封筒の色は白色とする
封筒の色は白色とします。茶色のものは請求書、見積書などビジネス用に使用しています。茶色を使用するとそれらに紛れてしまう可能性がありますから、避けた方が良いでしょう。ですが、茶封筒を使用したからといって選考に影響を与えることはありません。
- クリアフィルには、送付状(添え状)、履歴書、職務経歴書の順に挟む
クリアフィルに応募書類を挟むさいには順番があります。送付状(添え状)、履歴書、職務経歴書、その他の順に挟んで、封筒に入れましょう。
採用担当者が開封してクリアファイルから応募書類を取り出すとき、この順番が一般的であり、応募書類の確認をしやすくなります。
- 郵便局の窓口に出す
定型外の角形2号の封筒で職務経歴書などを提出する場合は、封筒の重さによって郵便料金が変わることもありますから、郵便局の窓口で重さを量って切手代金を支払うことをお勧めします。
切手を自分で貼って封筒をポストに投函すると、料金不足となって企業に迷惑がかかる恐れがありますから避けた方が良いでしょう。
まとめ
職務経歴書は折らないほうが良いけれど、必要なときの折り方について考えてみます。
転職活動で使用する職務経歴書や履歴書のフォーマットやサイズは指定する企業もありますが、多くの場合は用紙の指定はありません。
職務経歴書は、企業から特に指定がない限りA4サイズが一般的です。
職務経歴書は折らない、または二つ折りで封筒に入れることが望ましいです。A4サイズで作成、またはA3サイズの二つ折りだと採用担当者もスッキリと見やすくなります。
「角形2号」の封筒を使用すると、職務経歴書や履歴書などを挟んだクリアファイルが問題なく入りますので、「角形2号」を使用しましょう。
市販の職務経歴書や履歴書を買うと、三つ折りの折り方を想定した用紙の入る定型封筒が、一緒に入っているものもあります。
定型封筒に、三つ折りにした職務経歴書を入れて郵送することはマナー違反ではないですが、避けた方が無難です。
ですが、パート・アルバイト募集に応募のさい、または派遣会社や人材紹介会社に提出する場合は、定型封筒に三つ折りの応募書類はそれほど気にされません。
職務経歴書を三つ折りにする場合は、名前や写真が開封したときすぐに確認できる文章面を上にする外三つ折りにします。
職務経歴書の折り方以外にも、職務経歴書を郵送する場合に気をつけたいことは次の3つです。
- 封筒の色は白色とする
- クリアフィルには、送付状(添え状)、履歴書、職務経歴書の順に挟む
- 郵便局の窓口に出す
以上、職務経歴書は折らないほうが良いけれど、必要なときの折り方について解説しました。
最後に、キャリア育みファームでは、面接の必勝マニュアル「転職面接必勝法」を販売しています。
もちろん履歴書や職務経歴書の自己PRや志望動機などの作成にも役立つマニュアルとなっています。
会社側が採用の決め手として最も重視しているのは面接である‼
ということをご存知でしょうか。
面接対策には十分時間をかけることが大切です。具体的にどのように面接対策を進めていくのか、ほとんどの方は知りません。そんな方を支援したい一心で、必勝マニュアルを作成しております。
具体的な面接ノウハウが満載のマニュアルです。「なるほど、このようにすればいいのか」と理解して準備すれば、自信を持って面接に臨むことができ、ライバルからグンと抜け出すこと請け合いです。ぜひ、以下のページで詳細をご覧ください。
その他、以下のリンクも読み進めるとお役に立ちます。