【転職】職務経歴書の特記事項は「特になし」でも問題ない?
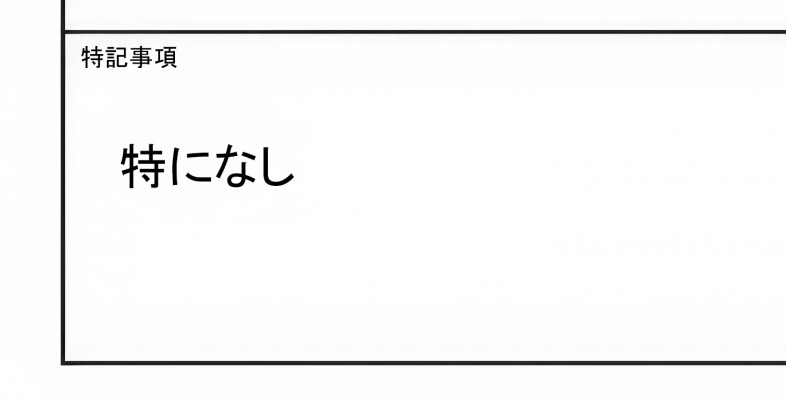
職務経歴書や履歴書の特記事項に何も記載するものがないとき、「特になし」と記入しても問題ないか悩む人は多いようです。
そもそも特記事項には何を記載したら良いのでしょうか?
職務経歴書の特記事項は「特になし」でも問題ないでしょうか?
職務経歴書や履歴書の特記事項の具体的な書き方はどのようなものでしょうか?
職務経歴書の特記事項の記載で気をつけたいことも知りたいものです。
本ブログは、職務経歴書の特記事項は「特になし」でも問題ないのかなどを解説します。
転職活動では、自己分析や企業研究した結果を基に履歴書や職務経歴書を作成し、一貫性をもたせて面接に繋げることを強く意識して臨んでください。
本サイト「キャリア育みファーム」を読んでいただければ、転職活動の選考・面接対策に自信が持てるようになります。さらに、絶対の自信を持って臨みたい方には、「転職面接必勝法」を用意しております。
職務経歴書の特記事項には何を記載するか
特記事項は「特になし」でも問題ないか検討する前に、特記事項とは何か理解しておきましょう。
- 特記事項とは何か
特記事項とは、職務経歴書や履歴書に自分として「特別に記載しておきたい事項」です。
- 採用されたとき、働くうえでの希望に関すること
- 学歴、職歴でイレギュラーがある場合の説明
- 自己PRまたは配慮してもらいたいこと
- 本人と連絡できる時間帯
以上のような企業にあらかじめ知ってもらいたいことを記載する項目です。職務経歴書などに特記事項があればこれらを記載することができます。
ですが、ほかの欄に記入した同じ内容をくりかえすことは、くどくなりますから避けてください。
- 職務経歴書に書く特記事項
- 職務経歴書と履歴書の特記事項は同じ内容としない
職務経歴書は、それまでの仕事の内容や実績、仕事を通じて培った能力・知識・スキルを具体的に応募先企業に伝えるための書類です。
一方、履歴書は基本的なプロフィールである、氏名・住所・学歴・職歴・保有資格・趣味・特技といった基本的なプロフィールを確認するための書類です。
特記事項は、職務経歴書と履歴書の両方にあります。それらが全く同じ内容だと、くどくなりますから、どちらか一方とするか、内容を別々にしたほうが良いでしょう。
- 職務経歴書にふさわしい特記事項とする
職務経歴書の意味を考慮すると、特記事項には職務経歴では伝えきれない選考で不利となるようなことを補足すると良いでしょう。
たとえば、空白期間や在籍期間が短い、転職回数の多さなどの理由などです。
あるいは、履歴書の特記事項のスペースは限られているために文字数に限りがあります。履歴書の特記事項で伝えきれないことを補足したり、追加したりすることもできます。
一方で、履歴書の特記事項には、スペースの範囲内で、働くうえでの希望に関すること、学歴、職歴でイレギュラーがある場合の説明、自己PRまたは配慮してもらいたいこと、本人と連絡できる時間帯、などを記載すれば良いでしょう。
以上のように、職務経歴書と履歴書の違いを理解して、それぞれの特記事項を適切に利用することが求められます。
- 職務経歴書と履歴書の特記事項は同じ内容としない
職務経歴書の特記事項は「特になし」でも問題ないか
職務経歴書の特記事項は「特になし」でもかまわないでしょうか。
上記について企業に特に知って欲しいことがないときでも、特記事項は空欄にしないことをお勧めします。
その理由として、採用担当者や面接官から、「記入を忘れたのではないか」「志望度が低いのではないか」と思われる可能性があるからです。
ですから、特記事項に書くものがないときは、「特になし」とすることで良くない印象を払拭することができます。
なお、実際には、「特になし」は素っ気ない印象がありますから、「特にありません」または、「貴社の規定に従います」としたほうが良いでしょう。
職務経歴書の特記事項の具体的な書き方
特記事項は「特になし」(「特にありません」「貴社の規定に従います」)としても問題ありません。
ですが、少しでも採用担当者や面接官にあらかじめ知っておいてほしいことがあれば、記載しておいたほうが、スムーズな選考を受けることができます。
特記事項は、「特になし」以外でも、簡潔にわかりやすくしてください。
それでは、職務経歴書の「特記事項」で「特になし」でない場合は、具体的には何をどのように記載したら良いか説明します。
- 空白期間が長い場合
空白期間が長いときは、特記事項にその理由を記入します。
空白期間が長い人は、「働けなかった事情は何か」「長く働き続けることができるか」と採用担当者や面接官に勘繰られる可能性があります。
企業に少しでも良い印象を与えられるように、「資格取得のため」「家族の介護」「病気療養」などによって就職が難しかったといった理由は必ず記入しておくと良いでしょう。
病気療養のため、○年○月~○年○月のブランクがあります。現在は完治し業務に支障はありません。
- 在籍期間が短い場合
在籍期間が短いと、「採用しても気に入らないことがあれば、すぐに退職してしまうのでは」と懸念されますから、安心してもらうためにも退職理由を簡潔に記載しましょう。
退職理由が企業側にあるとしても、前職を非難するとマイナスの印象を与えるため、そうならないためには本人の反省も加えると良いです。
募集職種と異なる職種に就くことを求められ、スキルアップにつながらないと判断して退職しました。自分として確認不足を反省しています。
- 転職回数が多い場合
転職回数が多いと、「採用しても堪え性がないので退職するかも知れない」と会社が懸念することがあります。
転職回数が多いけれど、前向きな転職理由があるときは「特記事項」に記入しても良いでしょう。
グローバルに活躍できる海外営業のプロを目指し、1社目で貿易の知識を深めながら語学を磨き、2社目の外資系企業に転職しました。3社目の現職では北米担当として現地の販売網の構築に携わっています。
以上については、職務経歴書ではなく、履歴書の特記事項を使用しても問題ありません。
履歴書の特記事項の具体的な書き方
履歴書の特記事項においても、「特になし」(「特にありません」「貴社の規定に従います」)としても問題ありませんが、「特になし」以外の具体的な書き方について説明します。
履歴書ではフォーマットに「特記事項」が組み込まれていることがほとんどのため、記入は必ずしなければなりません。
職務経歴書に比べてスペースは限られているため、職務経歴書よりも簡潔にする必要があります。
以下に履歴書の「特記事項」で具体的にはどのように書いたら良いか説明します。
- 働くうえでの希望に関すること
- 入社希望日
入社希望月日を事前に伝えたい場合は、特記事項に書くことができます。会社に勤務していながら中途採用に応募の場合は、採用となれば後任者への職務引継ぎをすることになりますから、退職予定日が決まっていないうちは書かないほうが良いでしょう。
在職中のため、入社は内定より1ヶ月後を希望します。
入社は、○月○日以降を希望します。(○月○日に現職を退職予定) - 希望する職種、勤務地
転職では、職種別募集が一般的ですから、希望職種を書く必要性は少ないですが、複数職種を募集している場合は、希望職種を明記しておきます。
希望勤務地について、本人の事情があれば「特記事項」に記します。
海外営業職を希望します。(転職)
○○県勤務を希望します。 - 転勤の不可
転勤のある会社に応募しても、やむを得ない事情で転居できない場合は、「特記事項」に記しておきましょう。
両親の介護のため、恐れ入りますが当面は転勤ができません。
- 転居予定
応募先企業が現住所より遠方のときは、本当に入社する気持ちがあるか採用担当者が疑問を持つことがあります。
安心させるためにも内定した後に転職先に合わせて転居することを「特記事項」に記しておくことをお勧めします。
採用となりましたときは、通勤可能な地域に転居を予定しています。
- 入社希望日
- 学歴、職歴でイレギュラーがある場合の説明
- 学校中退理由
高校や大学を中退したときは、「なぜ中退したのか」とネガティブにとらえられてしまうこともありますから、前向きな理由や、やむを得ない事情ならば「特記事項」に記入しておくと良いでしょう。
なお、中退の理由によっては書くことをためらうこともあります。その場合には特に書く必要はありませんが、面接では質問されますから、回答を用意しておいてください。
経済的事情により○○大学を中途退学しました。
- 空白期間が長い、在籍期間が短い、転職回数が多い場合の書き方は、職務経歴書の特記事項の具体的な書き方を参照ください。
- 学校中退理由
- 自己PRまたは配慮してもらいたいこと
- 資格取得予定
資格欄に記入できないけれど、資格取得のために勉強しているときは、「特記事項」欄でアピールできます。
資格がないために、その点での評価はされませんが、勉強する姿勢を認めてもらえることがあります。
ですが、入社後に資格を取得できないと良いイメージを持ってもらえませんので、必ず取得するという強い意志がないといけません。
簿記2級の資格取得を目指して勉強中です。
- 持病や治療中の病気
持病や、治療中の病気があり、就業日を使って定期的に通院が必要なときは、入社後の業務に支障がでないよう、「特記事項」欄に書いておくことをお勧めします。
そのために勤務時間や業務内容に配慮が必要な場合も、入社後に調整してもらえます。
持病により月1回の通院が必要なため、半休を希望します。それ以外には仕事をする上で支障はありません。
- 資格取得予定
- 本人と連絡できる時間帯
在職中で電話に出られない時間帯があるときは、連絡がつかない時間帯を「特記事項」に記入しておきましょう。
電話に出ないことが重なると、採用担当者の印象も悪くなります。
昼休みの○時から○時まで、または終業後の○時以降は電話対応が可能です。
以上の点が懸念されるならば、「特になし」ではなく、具体的に記載しておきましょう。
職務経歴書の特記事項の記入で気をつけたいこと
ここでは、その他、職務経歴書の特記事項の記入で気をつけたいことを説明します。
- 職務経歴書の特記事項は必須ではない
履歴書の特記事項に伝えたいことが全て記入できれば、あえて職務経歴書の特記事項に記載する必要はありません。
市販の職務経歴書に特記事項欄があれば、「特になし(「特にありません」)
と記入してください。職務経歴書をパソコンで作成するならば、特記事項欄を設けなくてもかまいません。
- 要望することが多くても、項目は絞る
たとえ要望することが多くても、全て伝えるのではなく、特に聞いてもらいたい項目に絞ることが肝心です。
あれもこれもと書き連ねると、入社してから扱いづらい人と思われてマイナス評価となってしまいます。
- 長い文章は避ける
特記事項はあくまで特別に何かあったときに使用する欄となっていて、必ず書かなければいけない欄ではありません。
そのため、自分が伝えたいことを長々と記載することは避けてください。特記事項はポイントを絞って、簡潔に一文で止めておき、面接で詳しく説明するほうがスマートです。
- 自分本位の希望を書かない
給与や賞与といった労働条件で希望の金額を書くことは避けてください。「未だ働いてもいないのにお金の要求なのか」と印象が良くありません。
同じように、残業や休日出勤はしたくない、というような自分勝手な要望もNGです。
また、入社後の希望職種や勤務地などを記すのはかまいませんが、「○○の仕事をしたい」と具体的な業務を記すと、「それが叶わなければ入社しないのか」と扱いにくい人と思われて不利です。
まとめ
職務経歴書の特記事項は「特になし」でも問題ないのか、書き方などを考えてみます。
特記事項とは、職務経歴書などに自分として「特別に記載しておきたい事項」です。
特記事項は、職務経歴書と履歴書の両方にあります。それらを全く同じ内容とするとくどくなりますから、同じ内容としないほうが良いです。
職務経歴書の意味を考慮すると、特記事項には職務経歴では伝えきれない選考で不利となるようなことを補足すると良いでしょう。
あるいは、履歴書の特記事項で記載しきれないことを補足したり、追加したりすることもできます。
職務経歴書の特記事項は、企業に特に知って欲しいことがないときでも空欄にしないことをお勧めします。
採用担当者や面接官から、「記入を忘れたのではないか」「志望度が低いのではないか」と思われる可能性があるからです。
ですから、特記事項に書くものがないときは、「特になし」とすることでマイナスの印象を払拭することができます。
実際は、「特になし」は素っ気ない印象がありますから、「特にありません」または、「貴社の規定に従います」としたほうが良いでしょう。
職務経歴書の「特記事項」で具体的には書く内容としては、次の3つです。
- 空白期間が長い場合の理由
- 在籍期間が短い場合の理由
- 転職回数が多い場合の理由
履歴書の特記事項においても、記入することがなければ、「特になし」(「特にありません」「貴社の規定に従います」)としても問題ありませんが、それ以外の具体的に書く内容は次の通りです。
- 働くうえでの希望に関すること
- 希望する職種、勤務地
- 学歴、職歴でイレギュラーがある場合の説明
- 自己PRまたは配慮してもらいたいこと
- 本人と連絡できる時間帯
職務経歴書の特記事項で気をつけたいことは、次の4つです。
- 職務経歴書の特記事項は必須ではない
- 要望することが多くても、項目は絞る
- 長い文章は避ける
- 自分本位の希望を書かない
以上、職務経歴書の特記事項は「特になし」でも問題ないのか、書き方などを解説しました。
最後に、キャリア育みファームでは、面接の必勝マニュアル「転職面接必勝法」を販売しています。
もちろん履歴書や職務経歴書の自己PRや志望動機などの作成にも役立つマニュアルとなっています。
会社側が採用の決め手として最も重視しているのは面接である‼
ということをご存知でしょうか。
面接対策には十分時間をかけることが大切です。具体的にどのように面接対策を進めていくのか、ほとんどの方は知りません。そんな方を支援したい一心で、必勝マニュアルを作成しております。
具体的な面接ノウハウが満載のマニュアルです。「なるほど、このようにすればいいのか」と理解して準備すれば、自信を持って面接に臨むことができ、ライバルからグンと抜け出すこと請け合いです。ぜひ、以下のページで詳細をご覧ください。
その他、以下のリンクも読み進めるとお役に立ちます。